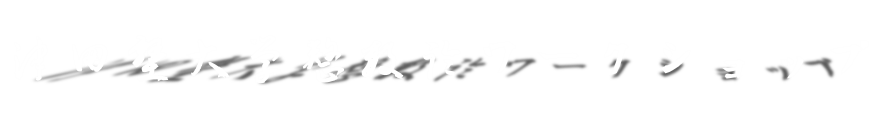津田塾大学整数論ワークショップ 2025
最終更新日:
講演概要
講演者五十音順・敬称略.講演概要の印刷用 pdf ファイルはこちらからどうぞ→![]()
記号凡例: ♭: 黒板での講演, ♯: プロジェクターでの講演
※ いずれの講演も,オンラインでの参加者には Zoom でのオンライン配信をいたします
Perfectoid towers arising from prisms
石塚 伶 (東京科学大学)♭
伊城–仲里–下元によって導入されたパーフェクトイドタワーの理論は,ネーター環とパーフェクトイド環を結びつける体系的な手法を与えている.しかし,既知のパーフェクトイド塔の例は限られていた.とくにネーターな例は(対数的)正則局所環に限られていた.本講演では,Bhatt–Scholze が導入した prism の概念を用いてこれまで知られていなかった特異な例を統一的に構成したことについて講演する.これにより,パーフェクトイドタワーの包括的な構成が可能となり,多くの新しい例が得られる.
On the gamma evaluation of (basic-)hypergeometric function via (q-)multiple zeta values
角野 裕太 (東北大学)♭
超幾何関数は数理科学の広範な分野に現れる重要な特殊関数であり,古くから盛んに研究されてきた.なかでも,特殊値における関数値をガンマ関数の閉形式で与える公式(これを gamma evaluation と呼ぶ)の体系的な決定法は未だ確立されておらず,既存の方法の多くはパラメータに特定の条件を課すことで得られている.本講演では,($q$-)多重ゼータ値の母関数を用いることにより,従来の枠組みでは扱えなかった ($q$-)超幾何関数に対する新しい gamma evaluation を与える手法を紹介する.
有限体上のある2パラメータ K3 曲面族のゼータ関数と Appell 関数
隈部 哲 (九州大学マス・フォア・インダストリ研究所)♯
超幾何関数はパラメータをもつ複素変数の級数として与えられる.一方で,有限体上の超幾何関数と呼ばれる,超幾何関数の有限体における類似の関数があり,超幾何関数が満たす様々な公式の類似や,多変数化などが現在も盛んに研究されている.もう一つの研究の方向として,有限体上定義された代数多様体族の有理点の個数との結びつきについての研究がある.本講演では,有限体上で具体的に与えられる2つの2パラメータ $K3$ 曲面族に対し,それらの有理点の個数から定まる (合同) ゼータ関数について講演者によって得られた結果を紹介する.特に Appell 関数と呼ばれる二変数超幾何関数とそれらに関する様々な公式を用いることで上記 $K3$ 曲面族のゼータ関数を二つの Legendre 楕円曲線族のゼータ関数の根を用いて記述する.
Arithmetic problems on parabolic parameters for quadratic polynomial maps
佐野 薫 (NTT 基礎数学研究センタ)♯
The parabolic parameters play an important role in the complex dynamics. In 1995, Morton and Vivaldi defined the polynomials whose roots are parabolic parameters for a one-parameter family of polynomial maps. We call these polynomials delta factors. Since the parabolic parameters involve the cyclotomic field, they are not only complex dynamical objects but also number theoretic objects. Morton and Vivaldi conjectured that the delta factors are irreducible over the rational field. However, it is still not known in general. Recently, we proved the irreducibility of the delta factors of period 3 for quadratic polynomials. In this talk, we introduce the parabolic parameters and some arithmetic problems arising around the parabolic parameters. This is a joint work with Junnosuke Koizumi, Yuya Murakami, and Kohei Takehira.
トーラスの二重被覆に関する Kaletha の理論の p=2 の場合への拡張に向けて
時本 一樹 (東京電機大学)♭
Kaletha は最近の研究で,非アルキメデス局所体 $F$ 上の簡約代数群 $G$ の極大トーラス $S$ に対して,$S(F)$ の二重被覆 $S(F)_{\pm}$ を導入し,これを用いると $G(F)$ の正則超尖点表現の指標公式や局所 Langlands 対応が簡明に表せることを証明した.本講演では,この理論の一部を説明してから,これを剰余標数 $p=2$ の場合に拡張するためのアイディアを紹介する.特に,指標公式に現れるある関数を,$p$ の偶奇によらずに構成する方法について述べる.(本講演は,Léo Gratien(シカゴ大学),Nhat Hoang Le(シンガポール国立大学)との共同研究に基づく.)
二次無理数に付随する Hecke 型 Dirichlet 級数の解析的性質
冨田 拓希 (理化学研究所)♯
無理数 $\alpha$ の自然数倍からなる数列 $(m\alpha)_{m=1}^\infty$ が $\mathrm{mod}\; 1$ で一様分布することが Weyl により知られている.Hecke はこの分布をより詳細に調べるために,$D\equiv 2,\, 3 \pmod{4}$ のときに $\alpha=\sqrt{D},\, \frac{1}{\sqrt{D}}$ に対して $\varphi(s,\alpha):=\sum_{m=1}^\infty\frac{\{m\alpha\}-\frac{1}{2}}{m^s}$ という関数を導入し,$\alpha=\sqrt{D},\, \frac{1}{\sqrt{D}}$ のときにその解析的性質を調べた.本講演では,Hecke の証明を一般化することにより,$D\equiv 1\pmod{4}$ のときに $\alpha=l\frac{1+\sqrt{D}}{2}, \, \frac{1}{l\sqrt{D}}$ $(l\in\mathbb{N})$ に対して $\varphi(s,\alpha)$ の解析的性質を調べた結果について紹介する.本研究は元慶應義塾大学の杉浦雅哉氏との共同研究に基づくものである.
モジュラー方程式と Hauptmodul の特殊値について
富山 和樹 (早稲田大学)♭
Monster 群の Moonshine によれば,Monster 群の無限次元表現から,McKay–Thompson 級数とよばれる $q$ 級数の系列が得られ,それらは Hauptmodul という特別なモジュラー関数になっている.Chen–Yui は一部の McKay–Thompson 級数について,モジュラー方程式という代数的関係式を構成することで,そのCM値が代数的整数となり虚2次体の環類体を生成するなど,$j$ 関数の singular moduli と類似の数論的性質をもつことを示した.本発表では,Cummins–Gannnon によって導入された一般モジュラー方程式という概念を用いることで,Chen–Yui の結果をすべての McKay–Thopson 級数を含むような Hauptmodul のクラスに拡張した研究を紹介する.応用として,$q$ 級数が完全再生性 (complete replicability) とよばれる組合せ論的性質をみたすという仮定から,(モジュラー不変性などを仮定しなくても) 特殊値の代数的整数性が保証されるという結果を紹介する.
Zhao’s method による保型 L 関数の臨界値の2進付値評価
野本 慶一郎 (株式会社光電製作所)♯
1997年に C. Zhao は,$\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ 上定義されたある楕円曲線 $y^2=x^3+Dx$ に付随する Hecke $L$ 関数の臨界値について,その代数的部分の2進付値の下界を与えた.その $2$ 進付値の評価手法は,パラメータ $D$ の異なる素因子の個数に基づく数学的帰納法を巧みに用いたものであり,しばしば Zhao’s method と呼ばれる.
Zhao’s method は様々な $L$ 関数への適用可能性をもつ汎用的な手法であり,実際,特定の条件を課した (weight 2, $\mathbb{Q}$ 係数) Hecke 固有形式に付随する保型 $L$ 関数に対して適用された結果がいくつか知られている.
本講演では,Zhao’s method を用いて評価可能とされてきた (weight 2, $\mathbb{Q}$ 係数) Hecke 固有形式に対する条件を大幅に緩和できたので,その成果を数値例と共に紹介する.また,その証明手法の詳細について述べる.本講演は足立大雅氏 (九州大) と椎井亮太氏 (九州大) との共同研究に基づく.
Torsion of elliptic curves over Qp with good reduction in cyclotomic extensions
吉田 学 (大和大学)♭
B. Mazur は1978年の論文において, $\mathbb{Q}$ 上の楕円曲線 $E$ の $\mathbb{Q}$ 有理点の成す群 $E(\mathbb{Q})$ の捩れ部分群として現れ得る群の分類を与えた. 2019年,M. Chou はこれを $\mathbb{Q}$ の最大アーベル拡大 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ の有理点へと拡張し, $E(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}})$ の捩れ部分群の分類を決定した. さらにこの Chou の結果に関連して, Gužvić–Vukorepa によって, $p=2,3,5,7,11$ および $0 \leq n \leq \infty$ に対する $E(\mathbb{Q}(\mu_{p^n}))$ の捩れ部分群の分類までもが与えられている.(ここで, $\mu_{p^n}$ は 1 の $p^n$ 乗根のなす群とする).本講演では,これらの結果の $p$ 進類似を与える.より正確には,$E$ を $\mathbb{Q}_p$ 上良還元をもつ楕円曲線とするとき,すべての素数 $p$ とすべての $0 \leq n \leq \infty$ に対して,$E(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^n}))$ の捩れ部分群を分類する.本研究は,小関祥康氏(神奈川大学)との共同研究である.
正標数の有理二重点と準 F-分裂 (小さな素数での例外的現象について)
呼子 笛太郎 (東京理科大学)♭
有理二重点 (RDP) とは,最も基本的な $2$ 次元の特異点のクラスである.複素数体上では,$\mathrm{SL}(2)$ の有限部分群による平面への自然な作用による商として現れる.さらに特異点の最小特異点解消に現れる例外因子の交わり方 (Dynkin図形) からその解析的な同型類が決定されることが知られている.この性質を taut 性という.正標数においても標数が $7$ 以上ならば taut 性が成り立つが,小さい標数では成り立たない.また正標数に特有の概念として,$F$-分裂性というものが知られている.RDP は標数 $7$ 以上であれば $F$-分裂であるが,やはり小さな標数ではそうではない.この講演では,$F$-分裂性を拡張した準 $F$-分裂性を導入し,全ての RDP が準 $F$-分裂であることを解説する.この研究は Kawakami–Takamatsu–Tanaka–Witaszek–Yoshikawa との共同研究である.